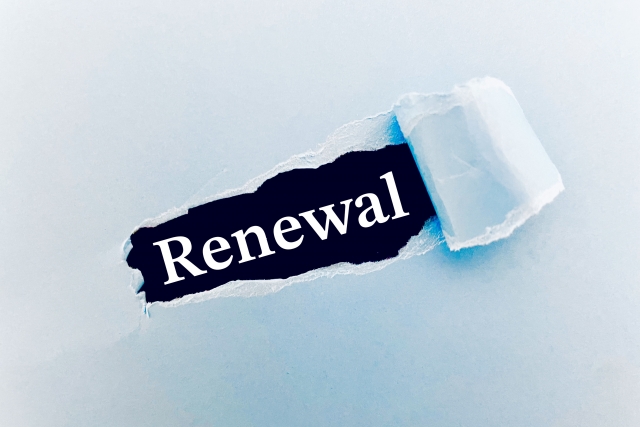こんにちは。盟生総研株式会社の足立です。
「そろそろWebサイトをリニューアルした方がいいのかな…?」
そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
デザインが古い、更新がしづらい、問い合わせが減った──。
理由はさまざまですが、リニューアルには“明確な目的と事前準備”が欠かせません。
実は、ただ見た目を変えるだけのリニューアルは失敗のもと。
アクセス数が落ちたり、問い合わせが減ったりと、「改修後に成果が下がる」ケースも多いのです。
この記事では、リニューアルを成功させるために必要な
- サイト改善のチェックリスト
- 失敗しがちな改修例
- 制作会社に依頼する際の検討ポイント
を、Webマーケティングの視点からわかりやすく解説します。
これからWebサイトをリニューアルする方はもちろん、
「今のサイトをどう改善すべきか迷っている」という方にも役立つ内容です。
なぜWebサイトのリニューアルが必要なのか?

リニューアルを検討する3つの主なタイミング
① デザインや情報が古くなっている
数年前に作ったサイトを今見ると、どこか“平成の香り”が漂う──そんなことはありませんか?
企業サイトや店舗サイトも、数年経つとデザインやユーザーの感覚が大きく変わります。
古い印象のままだと「この会社、動いていないのかな?」と不安を与えてしまうことも。
見た目だけでなく、掲載情報の鮮度も重要です。会社概要やサービス内容、料金なども最新に更新しましょう。
② 問い合わせ・売上が減少している
アクセスはあるのに問い合わせが減っている場合、導線やコンテンツ内容に問題があるかもしれません。
また、時代とともにユーザーの検索意図も変化します。以前は刺さったキャッチコピーや訴求も、今では響かないことも多いです。
数字が落ちたタイミングこそ、“見直しのサイン”と捉えるのが賢明です。
③ スマホ対応や機能面で時代遅れになっている
スマートフォンからのアクセスが7割を超える今、モバイル最適化は必須。
さらに、表示速度・SSL対応・フォームの簡易化など、細かなユーザビリティも成果に直結します。
「PCでは問題ないけどスマホだと見づらい」というサイトは、確実に機会損失しているといえるでしょう。
リニューアルの目的を明確にしないと失敗する理由
Webサイトのリニューアルで最も多い失敗は、「なんとなく新しくする」ことです。
目的が曖昧なまま進めると、完成した後に「結局何を改善したかったのか」が分からなくなってしまいます。
リニューアルのゴールは“デザインの更新”ではなく、“成果を出す設計”にあります。
「リニューアル=成功」とは限らない!よくある勘違いパターン
デザインを変えたからといって、問い合わせが増えるわけではありません。
むしろ構造変更でSEO順位が下がるケースも。
「新しい=良い」ではなく、「正しい目的設定×改善プロセス」が成功のカギです。
リニューアル前に必ず行うべき“サイト改善チェックリスト”



1. 現状のアクセス分析(どのページが見られているか?)
まず最初にやるべきは、「今のサイトがどう見られているか」を数字で把握すること。
Googleアナリティクスを使えば、人気ページ・離脱ページ・滞在時間が簡単に分かります。
感覚ではなくデータに基づいて、“改善すべき箇所”を特定しましょう。
2. CVR・直帰率・離脱率の確認方法
コンバージョン率(CVR)が低いページは、訴求や導線が弱い可能性があります。
また、直帰率が高いページは「期待と内容のズレ」があることが多いです。
ユーザーが“次に進みたくなる構成”になっているかを冷静に見直しましょう。
3. 競合サイトの分析で見えてくる改善ヒント
競合のWebサイトを見ることで、自社の強み・弱みが明確になります。
デザインの傾向や情報量、CTAの配置などを比較するだけでも多くの発見があります。
「他社がやっていること=真似すべき」ではなく、「自社らしさをどう出すか」を考える材料にしましょう。
4. SEO評価を落とさないための構造チェック
・URL構成やリダイレクト設定
既存ページのURLを変えると、検索エンジンは“別ページ扱い”します。
リニューアル時は、旧URL→新URLのリダイレクト設定を確実に行いましょう。
・メタ情報(タイトル・ディスクリプション)の継承
SEO評価を引き継ぐためには、タイトルやディスクリプションをコピーするだけでなく、
検索意図に合わせて最適化し直すのがベストです。
5. コンテンツの棚卸し(残す・消す・統合する)
過去の記事やページが増えすぎて、重複コンテンツになっているケースもあります。
“量より質”を重視して、アクセスがないページは削除または統合しましょう。
6. ページスピード・UI/UXの見直しポイント
読み込み速度はSEOにも大きく影響します。
また、ボタンやフォームが押しにくい、文字が小さい、導線が複雑──
そんな“小さなストレス”が離脱を生みます。デザインだけでなく“体験”の改善が大切です。
Webサイト改修で“失敗する”3つの落とし穴



1. デザイン優先で中身(導線)を軽視してしまう
「オシャレにしたい」「イメージを一新したい」という気持ちは分かります。
しかし、見た目ばかりにこだわると“使いにくいサイト”になりがちです。
Webサイトはアート作品ではなく、売上や問い合わせを生む仕組み。
デザインは“伝えるための手段”と心得ましょう。
2. SEOを無視してリニューアルし、検索順位が下落
リニューアル後にアクセスが激減する最大の原因は、SEOを考慮しなかったこと。
検索エンジンはサイト構造やリンク、メタ情報の変化に敏感です。
「公開してから調整すればいいや」は危険。設計段階からSEO専門家の意見を取り入れましょう。
3. リニューアル後の運用計画がない
新しいサイトを公開しても、更新が止まってしまえば意味がありません。
・更新ルールや担当者の明確化
誰が、どの頻度で、どんな情報を発信するのかを決めておくことで“運用の止まり”を防げます。
・PDCAを回すためのデータ管理体制
アクセス分析、SNS流入、CVデータを定期的に確認し、改善のPDCAを回しましょう。
【実例紹介】デザイン刷新で問い合わせが半減した失敗事例
ある企業では、デザインを最新化した直後に問い合わせが半減。
原因は、**「問い合わせボタンが下に埋もれてしまった」**ことでした。
どんなに美しいデザインでも、行動導線を削ってしまえば成果は出ません。
リニューアルは“美しさ”ではなく“使いやすさ”が命です。
成功するWebサイトリニューアルの進め方



1. 目的とKPIを明確に設定する
「問い合わせを増やしたい」「ブランドイメージを刷新したい」など、リニューアルには必ず“目的”があります。
しかし、漠然と「なんとなく良くしたい」では、成果は出ません。
目的を定量化し、KPI(重要指標)を設定しましょう。
例えば、
- 月間問い合わせ数を20%増やす
- 資料請求数を50件→80件にする
- 平均滞在時間を2分→3分に改善する
といった具体的な数値を決めることで、制作会社もゴールを共有しやすくなります。
2. 制作会社を選ぶ際のチェックポイント
リニューアルの成功は、パートナー選びで決まるといっても過言ではありません。
・実績や得意分野の確認
「デザインが得意な会社」「SEOが強い会社」「運用サポートが得意な会社」など、制作会社にもカラーがあります。
見た目の好みだけでなく、自社の目的に合った得意分野を持つ会社を選びましょう。
・見積もり項目の比較方法
見積もりを見ると、制作費・ディレクション費・コーディング費などが並びます。
注意したいのは「保守・運用費」「追加対応費用」がどう扱われているか。
安く見えても、納品後の修正が有料だったり、サポートがなかったりするケースも多いです。
“納品後にどこまで対応してもらえるか”を確認しておくことが大切です。
3. 内製 or 外注?それぞれのメリット・デメリット
内製化のメリットは、自社でスピーディに修正・更新ができること。
一方で、専門知識が不足すると、成果が出にくいというデメリットもあります。
外注の場合は、プロの手で高品質に仕上がりますが、費用とコミュニケーションの手間がかかります。
おすすめは、戦略や設計を外部と連携しながら、更新は社内で行う“ハイブリッド型”。
コストとクオリティのバランスを取りやすい方法です。
4. Web制作を検討する際に押さえるべき“契約・納品”の注意点
契約時にトラブルになりやすいのが、「データの所有権」と「納品範囲」。
特にCMS(WordPressなど)を使う場合、誰が修正できる状態で納品されるかを確認しましょう。
「修正のたびに制作会社に依頼しないといけない…」となると、運用コストが膨らみます。
また、納品形式(ZIPデータ・サーバーアップロード・Git管理など)も、契約書に明記しておくのが安全です。
リニューアル後にやるべき改善・検証作業



1. 公開直後にチェックすべき技術項目
公開直後は、まさに“最終テスト期間”。
・リンク切れや表示崩れの確認
ブラウザやデバイスごとに表示が崩れることはよくあります。
Chrome・Safari・Edge・iPhone・Android、それぞれでチェックしましょう。
・Google Search Consoleでのインデックス確認
新ページがGoogleに正しく認識されているかを確認します。
「noindexタグ」や「リダイレクト設定ミス」はSEOダウンの原因になるため注意が必要です。
2. リニューアル後のSEO順位変動を追う方法
順位はリニューアル直後に一時的に落ちることがあります。
これは自然な現象なので焦らず、2〜3ヶ月単位で経過を見守りましょう。
重要なのは、旧ページの評価を引き継げているか。
サーチコンソールやGoogleアナリティクスで、検索流入やクリック率の変化を追跡します。
3. アクセス・CVデータをもとにした改善サイクル
リニューアルは「完成」ではなく、「スタート」です。
公開後に得たデータを分析し、定期的に改善を重ねることで成果が伸びていきます。
たとえば、フォーム離脱率が高ければステップを減らす、CTAボタンを改善する──
小さな修正を重ねることで、大きな結果につながります。
4. 定期的な“運用型リニューアル”のすすめ
大規模なリニューアルを数年に一度するよりも、毎年少しずつ改良を重ねるのがおすすめです。
これがいわゆる「運用型リニューアル」。
検索エンジンのアルゴリズム変化にも柔軟に対応でき、コストも分散できます。
時代に合わせて“育てるサイト”を目指しましょう。
まとめ|“デザイン刷新”よりも“成果を上げる設計”を
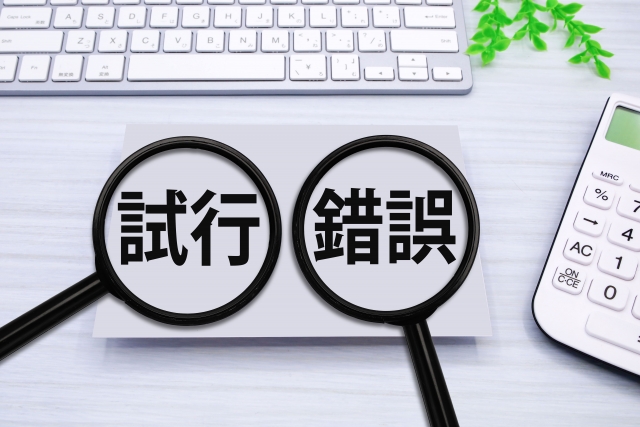
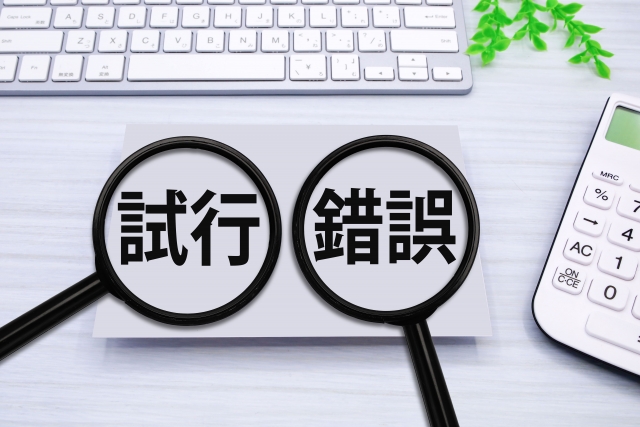
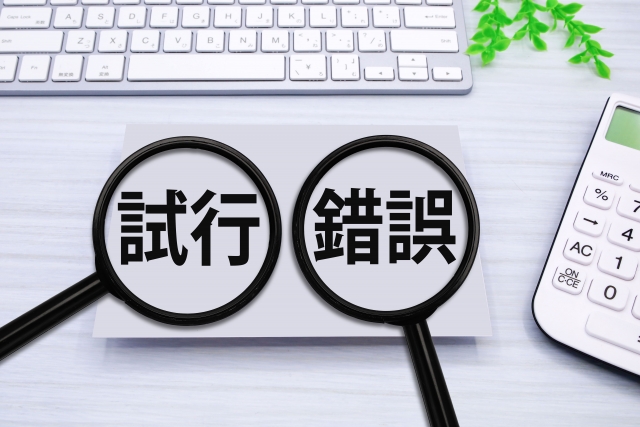
見た目の変更ではなく「成果を出す構造改革」が目的
Webサイトのリニューアルは、単なる「見た目のアップデート」ではありません。
「どうすれば問い合わせが増えるか」「どうすれば信頼が伝わるか」──
その答えを設計に落とし込むのが、本当のリニューアルです。
リニューアル成功のカギは“事前準備と分析”にある
現状分析を怠ると、課題が見えないままデザインを刷新して終わってしまいます。
アクセスデータ・SEO評価・ユーザー行動を把握し、根拠に基づいた設計を行うことが成功の第一歩です。
失敗を防ぐには、専門家の視点で現状を正確に把握すること
自分たちでは気づきにくい課題こそ、外部の専門家が冷静に見つけてくれます。
「第三者の視点」をうまく活用することで、ムダのない戦略的リニューアルが実現します。
📩 WEB集客・マーケティングの無料相談はこちら
「Webサイトをリニューアルしたいけど、どこから始めればいいか分からない」
「自社のサイトを客観的に診断してほしい」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
これまで500社以上のマーケティング支援を行ってきた盟生総研が、
あなたの事業に最適な“リニューアル設計”をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。